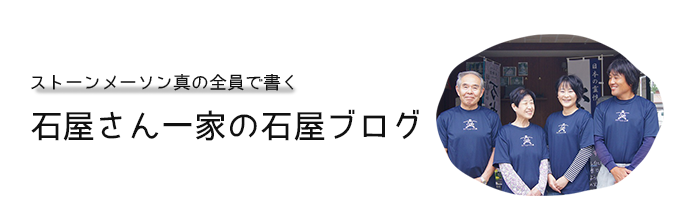2021年12月11日3:06 PM カテゴリー:
お墓のミニ知識
近年、お寺や神社にお参りして「御朱印」をいただくという人が増えています。
御朱印の起源については諸説あるものの、もともとは写経を奉納した証しとして
お寺からいただいたものをいい、現在では初穂料や納経料を納めることで、
参拝した証しとして多くの神社やお寺でいただくことができます。
御朱印は、御朱印帳に印章・印影を押印する形が多く、
押印の他には参拝した日付や寺社名、御祭
2021年11月14日3:06 PM カテゴリー:
お墓のミニ知識
「結婚式や新装開店は大安」という考え方は、現在でも根強く残っています。
もともとこの習慣は、古代中国で生まれた6種の曜で構成される「六曜」からきています。
「六曜」は、暦に記載される日時・方位の吉凶や運勢などの注記である暦注のひとつです。
「友引」の日に葬儀等を避けるようになったのは、平安時代に全盛を極めた陰陽道で「凶禍が友人に及ぶとする方角」
を「友引方」といい、それが六
2021年10月23日9:26 AM カテゴリー:
お墓のミニ知識
日本に存在する仏教の宗派は、「十三宗五十六派」といわれます。
天台宗・真言宗・浄土宗などの宗旨が13宗あり、さらにその分派が合わせて
56派あるという意味です。
宗旨によって呼び名は異なるものの、寺院には、総本山・本寺・中本寺・直末寺・孫末寺
など階層があって、この仕組みを「本末制度」といい、この中で最も上位にあって、
宗派に属する寺院を統括している代表を「総本山」と
2021年9月12日3:17 PM カテゴリー:
お墓のミニ知識
お線香は、お墓やお仏壇など仏式のご供養に欠かせないものです。
お線香を焚く理由のひとつとして「その場を清め、心を落ち着かせる」
という意味合いが知られています。
また経典でも、故人は四十九日(中陰)まで線香の香りを食べると言われ
「仏様が召し上がる供物」であると言われます。
また「立ち上る煙であの世とこの世をつなぎ、故人と対話する」、
「香煙が仏様をあの世まで導
2021年8月22日1:24 PM カテゴリー:
お墓のミニ知識
お盆のお墓参りの際に、お墓そうじをされる方も多いと思います。
改めて、夏の季節のお墓の掃除についてお伝えします。
お墓に到着したらまず軽く手を合わせ、お掃除のスタートです。
まずは枯れたお花やお線香の灰が残っている場合は処分します。
その後、枯葉など大きなごみから順に掃き掃除をします。
敷地内の草は除草したいところです。
その後、墓石を水拭きする等きれいにし、お
2021年7月10日9:35 AM カテゴリー:
お墓のミニ知識
「法要」と「法事」は言葉は似ていますが、意味は異なります。
まず「法要」は、読経していただき故人の冥福を祈る供養そのものを指します。
命日などの節目に行うもので、キリスト教では「追悼ミサ」「記念式」、
神道では「霊祭」がこれにあたります。仏教では「法要」を行う日が決まっており、
亡くなって七日ごとに行う忌日法要と、一周忌、三回忌などの年忌法要があります。
対して「法事
2021年6月20日4:14 PM カテゴリー:
お墓のミニ知識
とても似た言葉なので、混同してしまう方も多くいらっしゃいます。
永代供養とは、ご家族やご親族に代わって、宗教者等がずっと供養することを言います。
「永代供養料」とはその料金のことを指しています。
対して「永代使用料」とは、
この墓地を永年に渡って使用する権利に対する料金のことです。
多くの場合どちらも最初に一括して支払いますが、「永代供養料」には
納骨後定期的に
2021年5月27日4:50 PM カテゴリー:
お墓のミニ知識
ここ数年、よく耳にするようになった「終活」という言葉。
以前には流行語大賞にもノミネートされ話題になりました。
「人生の終わりのための活動」を略したもので、
人生の最期の時を迎えるにあたり、いろいろな準備をすることをいいます。
具体的には、エンディングノートの作成や遺言、
お葬式やお墓や相続などについて考えて、準備をすすめていくことです。
以前は、自分自身の死を
2021年4月24日11:24 AM カテゴリー:
お墓のミニ知識
硬い石材で作られているお墓は「建てたらずっと綺麗なままでしょう?」と思われるかもしれませんが、
お墓にも「お手入れ」が必要です。
石材は天然の物、年月とともに少しずつ経年劣化します。
墓石によく使用されている「みかげ石」等は非常に耐久性に優れた石です。
しかしお墓を長持ちさせるためは「いい石を選ぶ」だけでなく、
「お手入れ」がポイントです。
特に石と石の継ぎ目の